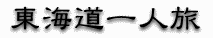 | 49.関宿〜坂下宿へ(街道地図) |
| 三重県鈴鹿郡関町→東の追分→関宿→地蔵院→市瀬→沓掛(7km:2.5時間) |
■ 関宿について ■(2000年3月17日)晴・一時雹雨  世間では朝令暮改、ファジィー、風見鶏と散々の俺だが、
街道歩きで本領発揮!
自然の変化や移り変わる景色に心は素直に染まる。
深く考える事は無いのだ。旅はそれでいいのだ。
水のように・・風のように・・そして雲のように・・心は流れるままがいい。
・・・・
関宿は古代から交通の要衝で「伊勢鈴鹿の関」が置かれていた場所である。
関の名も鈴鹿の関に由来する。
西追分の大和街道や東追分の伊勢別街道が東海道と分岐し、
これらの街道を参勤交代や伊勢参りなどで利用する人々で賑わっていた。
現在でも、宿場町の景観が1.8kに渡り残されている。
世間では朝令暮改、ファジィー、風見鶏と散々の俺だが、
街道歩きで本領発揮!
自然の変化や移り変わる景色に心は素直に染まる。
深く考える事は無いのだ。旅はそれでいいのだ。
水のように・・風のように・・そして雲のように・・心は流れるままがいい。
・・・・
関宿は古代から交通の要衝で「伊勢鈴鹿の関」が置かれていた場所である。
関の名も鈴鹿の関に由来する。
西追分の大和街道や東追分の伊勢別街道が東海道と分岐し、
これらの街道を参勤交代や伊勢参りなどで利用する人々で賑わっていた。
現在でも、宿場町の景観が1.8kに渡り残されている。
|
■ 小万のもたれ松〜東の追分 ■約5〜600m   国道を越え狭い街道に小万のもたれ松(写真左)がある。
(「関の小万が亀山通い、月に雪駄が二五足」
と鈴鹿馬子唄に歌われた小万(少女)は
父の仇を討つために関宿から亀山宿まで
剣術の稽古に通っていた。その小万が、
若者の戯れを避けるため身を隠した松)
すぐ先に鳥居が見え、常夜燈や一里塚があった。東の追分(写真中)だ。
鳥居の道は伊勢への別街道で東海道は真っ直ぐ
西の追分まで夢のような家並みが続く。
国道を越え狭い街道に小万のもたれ松(写真左)がある。
(「関の小万が亀山通い、月に雪駄が二五足」
と鈴鹿馬子唄に歌われた小万(少女)は
父の仇を討つために関宿から亀山宿まで
剣術の稽古に通っていた。その小万が、
若者の戯れを避けるため身を隠した松)
すぐ先に鳥居が見え、常夜燈や一里塚があった。東の追分(写真中)だ。
鳥居の道は伊勢への別街道で東海道は真っ直ぐ
西の追分まで夢のような家並みが続く。
|
■ 関宿・御馳走場 ■約5〜600m   町並み(写真左)は東から、木崎・中町・新所の3地区で形成されている。
この街道は歩く姿が良く似合う。
全てが本物の胸高鳴る世界だ。
前を観ても振返っても美しい。
中ほどに御馳走場(写真中)があった。
(宿場に出入りする大名行列を、宿役人が出迎えたり見送ったりした場所)
中町の百五銀行辺り(写真右)から西を観ると微かに鈴鹿峠を遠望できる。
町並み(写真左)は東から、木崎・中町・新所の3地区で形成されている。
この街道は歩く姿が良く似合う。
全てが本物の胸高鳴る世界だ。
前を観ても振返っても美しい。
中ほどに御馳走場(写真中)があった。
(宿場に出入りする大名行列を、宿役人が出迎えたり見送ったりした場所)
中町の百五銀行辺り(写真右)から西を観ると微かに鈴鹿峠を遠望できる。
|
■ 延命寺・鶴屋・百六里庭 ■約2〜300m   右路地奥に旧川北本陣の門を移築した延命寺(写真左)がある。
街道の中心は関まちなみ資料館・脇本陣もつとめた旅篭鶴屋(写真中)・百六里庭(写真右)
があり、江戸の昔を教えてくれる。
(関まちなみ資料館=関町大字中町482: 05959-2404、
江戸時代の関宿の町屋を再現した資料館)
(百六里庭=町並みの中の小公園。関宿が江戸から百六里の距離に
有る事から名付けられた。通りに面した建物、眺関亭
からは、関宿の町並みが見渡せる)
右路地奥に旧川北本陣の門を移築した延命寺(写真左)がある。
街道の中心は関まちなみ資料館・脇本陣もつとめた旅篭鶴屋(写真中)・百六里庭(写真右)
があり、江戸の昔を教えてくれる。
(関まちなみ資料館=関町大字中町482: 05959-2404、
江戸時代の関宿の町屋を再現した資料館)
(百六里庭=町並みの中の小公園。関宿が江戸から百六里の距離に
有る事から名付けられた。通りに面した建物、眺関亭
からは、関宿の町並みが見渡せる)
|
■ 玉屋・関の戸・小万の碑 ■約2〜300m  旅篭玉屋(写真左)は「関で泊まるなら鶴屋か玉屋、まだも泊まるなら会津屋か」
と謡われたほど関宿を代表する大旅篭のひとつ。現在は歴史資料館になっている。
先程の「まちなみ資料館」と共通で入館料=300円。休館日=月・年末年始。
対面は庵看板の銘菓・関の戸本舗
(餡を薄皮餅で包んだ上に和三盆の糖をふりかけた和菓子)
その先右奥に関の小万(写真右)が眠る福蔵寺。
・・・関の小万について=
同僚に殺された久留米藩士
牧藤左衛門の妻は、仇を追って
関まで来たが、旅篭山田屋で
女子を産んで死亡。旅篭の主人
は、この子を小万と名付けて
養育した。小万は親の悲劇を
知らされ、亀山で剣術修行をし
やがて仇を発見し討ち果たした。
その後、恩有る山田屋で奉公し36才で亡くなった。
旅篭玉屋(写真左)は「関で泊まるなら鶴屋か玉屋、まだも泊まるなら会津屋か」
と謡われたほど関宿を代表する大旅篭のひとつ。現在は歴史資料館になっている。
先程の「まちなみ資料館」と共通で入館料=300円。休館日=月・年末年始。
対面は庵看板の銘菓・関の戸本舗
(餡を薄皮餅で包んだ上に和三盆の糖をふりかけた和菓子)
その先右奥に関の小万(写真右)が眠る福蔵寺。
・・・関の小万について=
同僚に殺された久留米藩士
牧藤左衛門の妻は、仇を追って
関まで来たが、旅篭山田屋で
女子を産んで死亡。旅篭の主人
は、この子を小万と名付けて
養育した。小万は親の悲劇を
知らされ、亀山で剣術修行をし
やがて仇を発見し討ち果たした。
その後、恩有る山田屋で奉公し36才で亡くなった。
|
■ 地蔵院・門前町(会津屋) ■約5〜600m   行く手に見える大きな屋根は関の地蔵院(写真左)
(東海道を旅する人々に親しまれた関の地蔵さんは
我国最古の地蔵菩薩で一休禅師が地蔵の首に自分の赤い褌をかけ、
小便までかけて開眼供養したとされている。
国重要文化財)
門前にある(写真中)会津屋(山田屋)は小万が育った旅篭として知られている。
中町を過ぎ新所地区に入ると今まで無かった電柱が見えてきた。
右に関の特産・鉄砲に用いる火縄屋が(写真右)並ぶ。
行く手に見える大きな屋根は関の地蔵院(写真左)
(東海道を旅する人々に親しまれた関の地蔵さんは
我国最古の地蔵菩薩で一休禅師が地蔵の首に自分の赤い褌をかけ、
小便までかけて開眼供養したとされている。
国重要文化財)
門前にある(写真中)会津屋(山田屋)は小万が育った旅篭として知られている。
中町を過ぎ新所地区に入ると今まで無かった電柱が見えてきた。
右に関の特産・鉄砲に用いる火縄屋が(写真右)並ぶ。
|
■ 西の追分・市瀬集落 ■約1km   家並みを抜けると西の追分に出た。ここは伊賀上野、奈良に至る
大和街道の分岐点で、旅人の道中安全を祈願して建立したという
「ひたりハいかやまとみち」(写真左)の石碑が残ってる。
ここまでは夢のようだったが・・・
国道を歩くとイキナリ冷たい雹雨の嵐(写真中)に襲われた。
写真ではお伝え出来ないが最大の試練だった。氷入りの雨は冷たい。
ずぶ濡れ状態で100m程進んだが撤退した。後戻りは初めてだった。
態勢を整え再び市瀬地区(写真右)へと進んだ。
家並みを抜けると西の追分に出た。ここは伊賀上野、奈良に至る
大和街道の分岐点で、旅人の道中安全を祈願して建立したという
「ひたりハいかやまとみち」(写真左)の石碑が残ってる。
ここまでは夢のようだったが・・・
国道を歩くとイキナリ冷たい雹雨の嵐(写真中)に襲われた。
写真ではお伝え出来ないが最大の試練だった。氷入りの雨は冷たい。
ずぶ濡れ状態で100m程進んだが撤退した。後戻りは初めてだった。
態勢を整え再び市瀬地区(写真右)へと進んだ。
|
■ 筆捨山〜沓掛 ■約2〜3km   14:20(28867歩)弱気になってホテルに帰らなくて良かった。
市瀬を抜け国道沿いの筆捨山標柱(写真左)辺りからカラリと晴れてきたのだ。
(筆捨山=景色に圧倒されたか急変する天候に描けなかったのか絵師が筆を捨てたため
名付けられた)
やがて国道から離れ右の旧道へ入り
鈴鹿川を左(写真中)に沓掛の集落(写真右)を歩く、沓掛公民館辺りで
親切そうなお母さん(田中家)
に関交通タクシー(0595-96-0300)の電話を聞いておいた。
この先、何が起こるか判らない。
14:20(28867歩)弱気になってホテルに帰らなくて良かった。
市瀬を抜け国道沿いの筆捨山標柱(写真左)辺りからカラリと晴れてきたのだ。
(筆捨山=景色に圧倒されたか急変する天候に描けなかったのか絵師が筆を捨てたため
名付けられた)
やがて国道から離れ右の旧道へ入り
鈴鹿川を左(写真中)に沓掛の集落(写真右)を歩く、沓掛公民館辺りで
親切そうなお母さん(田中家)
に関交通タクシー(0595-96-0300)の電話を聞いておいた。
この先、何が起こるか判らない。
|
■ 鈴鹿馬子唄会館・小学校跡〜坂下 ■約2〜3km   沓掛を抜けると道は二又になる。角は
「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山雨が降る」で有名な
鈴鹿馬子唄会館だ。右の旧道に東海道の宿場名を記した木柱が並んで(写真左)いた。
坂の上には鈴鹿峠自然の家(小学校跡)(写真中)の広いグランドが見える。
先程の二又の道と合流し坂下宿へ(写真右)と入って行った。(15:00着)
沓掛を抜けると道は二又になる。角は
「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山雨が降る」で有名な
鈴鹿馬子唄会館だ。右の旧道に東海道の宿場名を記した木柱が並んで(写真左)いた。
坂の上には鈴鹿峠自然の家(小学校跡)(写真中)の広いグランドが見える。
先程の二又の道と合流し坂下宿へ(写真右)と入って行った。(15:00着)
・・・16時、伊勢坂下のバス停周辺を1時間以上も徘徊している怪しげな男がいた・・ (行程2.5時間(計7時間)・2000.3/17(金):万歩計=32288) |
旅人:浮浪雲
48.亀山宿〜関宿へ
 50.坂下宿〜土山宿へ
50.坂下宿〜土山宿へ
|