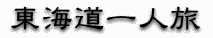 | 48.亀山宿〜関宿へ(街道地図) |
| 三重県亀山市→亀山城→京口坂→野村一里塚→布気神社→鈴鹿川(6km:2時間) |
■ 亀山宿について ■(2000年3月17日)雨→晴 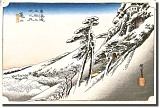 天気のせいか、どうも時間の経過が掴めない。まだ10時半なのに
相当な時間を歩いているような気がする。
・・・
今回の東海道歩きは強行軍だ、
特に今日は1日数便のバスを坂下宿で利用するのでどうしても16:14迄に
到着しなければならない。(2017.11現在、伊勢坂下行バスは関駅前に路線変更)
・・・・
亀山城は戦国時代に丘陵状の地形を利用し築かれた城である。
城の櫓や白壁が蝶の舞うように見えることから粉蝶城とも呼ばれた。
この六万石の城下町とともに亀山宿は繁栄したが、
藩領内に幕府直轄の宿場が置かれていたため、参勤交代で通る
大名は亀山宿の泊りを避けたという。
天気のせいか、どうも時間の経過が掴めない。まだ10時半なのに
相当な時間を歩いているような気がする。
・・・
今回の東海道歩きは強行軍だ、
特に今日は1日数便のバスを坂下宿で利用するのでどうしても16:14迄に
到着しなければならない。(2017.11現在、伊勢坂下行バスは関駅前に路線変更)
・・・・
亀山城は戦国時代に丘陵状の地形を利用し築かれた城である。
城の櫓や白壁が蝶の舞うように見えることから粉蝶城とも呼ばれた。
この六万石の城下町とともに亀山宿は繁栄したが、
藩領内に幕府直轄の宿場が置かれていたため、参勤交代で通る
大名は亀山宿の泊りを避けたという。
|
■ カメヤマローソク〜亀山宿 ■約1km   国道を越えてすぐ左に日本一のシェアを誇る「カメヤマローソク」(写真左)の本社
がある。栄町から宿場の雰囲気(写真中)が残る本町を歩いていると何やらお城(写真右)が見える。
小田原宿や藤川宿で見かけた天守閣を模した商店の建物だった。
旧道の本町商店街は連子格子を見せながら、
この先、江戸口門跡まで続き、東海道を感じさせてくれた。
大通りの銀行角を右に曲がると近代的な商店街になる。
国道を越えてすぐ左に日本一のシェアを誇る「カメヤマローソク」(写真左)の本社
がある。栄町から宿場の雰囲気(写真中)が残る本町を歩いていると何やらお城(写真右)が見える。
小田原宿や藤川宿で見かけた天守閣を模した商店の建物だった。
旧道の本町商店街は連子格子を見せながら、
この先、江戸口門跡まで続き、東海道を感じさせてくれた。
大通りの銀行角を右に曲がると近代的な商店街になる。
|
■ 亀山城多聞櫓・侍屋敷遺構 ■約5〜600m   アーケードをそのまま真っ直ぐ歩き亀山城に直行した。
(亀山城=亀山藩六万石の居城で黒板張りの多聞櫓と石垣が現存し、
当時と変わらぬ風情を残す。桜や積雪の頃は広重描く「亀山雪晴」を
映しだす。三重県の史跡に指定)
・・今まで観て来た多くの城は威圧的だったが、この亀山城は庶民的な感じで親しみやすい城郭だ・・
城下には藩家老の加藤内膳家長屋門と土蔵(侍屋敷遺構)写真右が今でも残っている。
アーケードをそのまま真っ直ぐ歩き亀山城に直行した。
(亀山城=亀山藩六万石の居城で黒板張りの多聞櫓と石垣が現存し、
当時と変わらぬ風情を残す。桜や積雪の頃は広重描く「亀山雪晴」を
映しだす。三重県の史跡に指定)
・・今まで観て来た多くの城は威圧的だったが、この亀山城は庶民的な感じで親しみやすい城郭だ・・
城下には藩家老の加藤内膳家長屋門と土蔵(侍屋敷遺構)写真右が今でも残っている。
|
■ 城下・京口門跡 ■約5〜600m   街道に戻る事にする。青木門跡(写真左)や街道沿いに飯沼慾斎(幕末植物学者)生誕地が
あった。宿場の家並みを抜けると梅厳寺門前の京口門跡(写真右)に至る。
(京口門跡=1672年、
東海道の番所として亀山藩主板倉重常によって築かれた。
石垣に冠木門、棟門、白壁の番所は「亀山に過ぎたるものの二つあり
伊勢屋蘇鉄に京口御門」と謡われたほど壮観であった。広重亀山雪晴はこの場所から描いたと言われている)
街道に戻る事にする。青木門跡(写真左)や街道沿いに飯沼慾斎(幕末植物学者)生誕地が
あった。宿場の家並みを抜けると梅厳寺門前の京口門跡(写真右)に至る。
(京口門跡=1672年、
東海道の番所として亀山藩主板倉重常によって築かれた。
石垣に冠木門、棟門、白壁の番所は「亀山に過ぎたるものの二つあり
伊勢屋蘇鉄に京口御門」と謡われたほど壮観であった。広重亀山雪晴はこの場所から描いたと言われている)
|
■ 京口坂〜野村一里塚 ■約1km   ここが亀山宿の西出口だ。京都へ向かう東海道(写真左)はなだらかな下り道になる。右下に照光寺(写真中)。
11時を過ぎ、適当な食堂も見当たらないので念のため街道途中の雑貨屋(八百屋兼用)でパンを買う。
やがて、右に異様な大きさの野村一里塚(写真右)に遭遇。
(野村一里塚=東海道一里塚としてほぼ完全な形を残している。
樹齢400年の椋(むく)の木で幹囲6m、高さ30mの巨木
は国の史跡に指定されている。)
ここが亀山宿の西出口だ。京都へ向かう東海道(写真左)はなだらかな下り道になる。右下に照光寺(写真中)。
11時を過ぎ、適当な食堂も見当たらないので念のため街道途中の雑貨屋(八百屋兼用)でパンを買う。
やがて、右に異様な大きさの野村一里塚(写真右)に遭遇。
(野村一里塚=東海道一里塚としてほぼ完全な形を残している。
樹齢400年の椋(むく)の木で幹囲6m、高さ30mの巨木
は国の史跡に指定されている。)
|
■ 大庄屋屋敷跡〜布気神社 ■約1km   淡々とした道を歩き、やがて民家が現れてくると茶畑の中に大庄屋屋敷跡(写真左)の標柱
があった。その先で道が別れるが街道らしい右の道(写真中)へ行ってみる。
途中に布気神社があったので間違いなく東海道だ。
遠くに見える街道の家並み(写真右)に誘われ坂を降りていく。
国道を渡る跨道橋下のレストランオスカーでミンチ定食(江戸ではメンチ定食)をオーダー。
ここのママさんは気さくで東海道歩きを応援してくれた。
淡々とした道を歩き、やがて民家が現れてくると茶畑の中に大庄屋屋敷跡(写真左)の標柱
があった。その先で道が別れるが街道らしい右の道(写真中)へ行ってみる。
途中に布気神社があったので間違いなく東海道だ。
遠くに見える街道の家並み(写真右)に誘われ坂を降りていく。
国道を渡る跨道橋下のレストランオスカーでミンチ定食(江戸ではメンチ定食)をオーダー。
ここのママさんは気さくで東海道歩きを応援してくれた。
|
■ 大岡寺畷・鈴鹿川 ■約1〜2km   店を出た頃(12:00)から雨もすっかり上がり空はキラキラと晴れ渡ってきた。
・・やっぱり東海道はこれでなくっちゃ〜!・・
♪さぁ行きますか〜!(MP3)
・・旅人の気分は最高潮に達し鈴鹿川(写真右)は春になった。
大岡寺畷、名阪国道高架下の絵パネルを軽快に歩き抜けていた。
国道を渡ればもうすぐ関宿だ。
店を出た頃(12:00)から雨もすっかり上がり空はキラキラと晴れ渡ってきた。
・・やっぱり東海道はこれでなくっちゃ〜!・・
♪さぁ行きますか〜!(MP3)
・・旅人の気分は最高潮に達し鈴鹿川(写真右)は春になった。
大岡寺畷、名阪国道高架下の絵パネルを軽快に歩き抜けていた。
国道を渡ればもうすぐ関宿だ。
・・・お昼過ぎ、鈴鹿川の土手に立ち止まり、ゆったりと時空を楽しむ旅人がいた・・ (行程2時間・2000.3/17(金):万歩計=計測中) |
旅人:浮浪雲
47.庄野宿〜亀山宿へ
 49.関宿〜坂下宿へ
49.関宿〜坂下宿へ
|