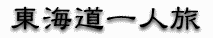 | 19.興津宿〜江尻宿へ(街道地図) |
| 静岡県清水市興津中町→興津川→宿場→清見寺→山門→細井の松(4km:1.5時間) |
■ 興津宿について ■(1999年9月23日)曇 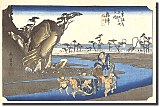 泥の中から脱出したが新しいウォーキングシューズは惨めな姿となった。
墓地のそばにあった案内板と車の轍に惑わされ右に行ったのが
間違いの元だった。俺の行く道は左斜め前方なのだ!道が無くとも行くべきだった。
お陰で雨の降る造成中の赤土で泥だらけになってしまったのだ。
興津宿は薩垂峠を越えホッと一息出来る、江戸から17番目の宿場である。
清見潟を見下ろす風光明媚な地と共に
箱根のような関所が置かれ軍事・交通の要所でもあった。明治以降は
元勲たちの別荘地としても有名だ。
泥の中から脱出したが新しいウォーキングシューズは惨めな姿となった。
墓地のそばにあった案内板と車の轍に惑わされ右に行ったのが
間違いの元だった。俺の行く道は左斜め前方なのだ!道が無くとも行くべきだった。
お陰で雨の降る造成中の赤土で泥だらけになってしまったのだ。
興津宿は薩垂峠を越えホッと一息出来る、江戸から17番目の宿場である。
清見潟を見下ろす風光明媚な地と共に
箱根のような関所が置かれ軍事・交通の要所でもあった。明治以降は
元勲たちの別荘地としても有名だ。
|
■ 下り道・途切れ道 ■約1km   泥沼を抜けると左手に海を見ながらの細い下り坂となる。
坂を降りると民家が(写真左)現れる。そのまま旧道らしき道を行くと、とうとう袋小路に
なってしまった。線路の先に旧道(写真中)が見える。
左右を確認して渡った。自転車も渡れるような台が置いてあったから、日常生活の
道路みたいだ。そして興津川が見えてきた。歩道の無い橋(写真右)だけど気をつけて右側通行。
泥沼を抜けると左手に海を見ながらの細い下り坂となる。
坂を降りると民家が(写真左)現れる。そのまま旧道らしき道を行くと、とうとう袋小路に
なってしまった。線路の先に旧道(写真中)が見える。
左右を確認して渡った。自転車も渡れるような台が置いてあったから、日常生活の
道路みたいだ。そして興津川が見えてきた。歩道の無い橋(写真右)だけど気をつけて右側通行。
|
■ 宿場中心 ■約1〜2km   橋を越え大きな道路を突き進む。
右手には宗像神社(女体の森)があったらしいが気がつかなかった。
やがて「石塔寺跡」(写真左)に髭題目と呼ばれる石標が建っていた。今日はお彼岸なのか供え物
が置かれていた。(両親の墓参りもしないで歩いていた事に気づく・反省)
(髭題目=興津宿から身延、甲府に至る道は、身延道とも呼ばれた。
この分岐点にある石標はヒゲが跳ねたような文字で「南無妙法蓮華経」と書かれており「髭題目」と呼ばれている)
その先、橋を渡ると本陣跡があり宿場中心に入る。本町公民館前には大きなソテツ
があった。
橋を越え大きな道路を突き進む。
右手には宗像神社(女体の森)があったらしいが気がつかなかった。
やがて「石塔寺跡」(写真左)に髭題目と呼ばれる石標が建っていた。今日はお彼岸なのか供え物
が置かれていた。(両親の墓参りもしないで歩いていた事に気づく・反省)
(髭題目=興津宿から身延、甲府に至る道は、身延道とも呼ばれた。
この分岐点にある石標はヒゲが跳ねたような文字で「南無妙法蓮華経」と書かれており「髭題目」と呼ばれている)
その先、橋を渡ると本陣跡があり宿場中心に入る。本町公民館前には大きなソテツ
があった。
|
■ 清見寺・五百羅漢 ■約500m   やがて東海道ガイドブックで見たことが有る清見寺の門(写真左)が見えてきた。
来てみて判ったことだが境内の中を線路(写真中)が通っているのだ。
清見寺=白鳳時代、清見が関と共に創建されたという古刹。
足利尊氏・今川義元らが清見寺を手厚く保護した。
境内左には五百羅漢(写真右)がいる(亡くなった方にそっくりな顔が見つかるといわれています)
写真撮影時は皆さんに向かって何度も頭を下げて撮らしてもらったが
大勢に見つめられているようでカラオケ状態だった。
やがて東海道ガイドブックで見たことが有る清見寺の門(写真左)が見えてきた。
来てみて判ったことだが境内の中を線路(写真中)が通っているのだ。
清見寺=白鳳時代、清見が関と共に創建されたという古刹。
足利尊氏・今川義元らが清見寺を手厚く保護した。
境内左には五百羅漢(写真右)がいる(亡くなった方にそっくりな顔が見つかるといわれています)
写真撮影時は皆さんに向かって何度も頭を下げて撮らしてもらったが
大勢に見つめられているようでカラオケ状態だった。
|
■ 波多打川辺りの旧道 ■約1〜2km   この先に静清バイパスを潜る(写真左)イベントが見えてきた。写真バス停のベンチで一休みする。
自販機も付いていて便利だ。今日は涼しい。この分なら江尻に3時前に着きそうだ。
そしたら清水次郎長の生家まで行ってみよう。
波多打川を渡るとスグ左に旧道がある。竹簾が目立つ町並みを抜けて東海道本線の踏切りを渡る。
民家の玄関先(写真中)に日の丸国旗が目立つ、法律で決まったのだ。東海道は紺暖簾が似合うのだが・・
そして国道と合流する地点に秋葉山常夜燈(写真右)が見えた。
この先に静清バイパスを潜る(写真左)イベントが見えてきた。写真バス停のベンチで一休みする。
自販機も付いていて便利だ。今日は涼しい。この分なら江尻に3時前に着きそうだ。
そしたら清水次郎長の生家まで行ってみよう。
波多打川を渡るとスグ左に旧道がある。竹簾が目立つ町並みを抜けて東海道本線の踏切りを渡る。
民家の玄関先(写真中)に日の丸国旗が目立つ、法律で決まったのだ。東海道は紺暖簾が似合うのだが・・
そして国道と合流する地点に秋葉山常夜燈(写真右)が見えた。
|
■ 細井の松原 ■約1〜2km   東光寺山門(写真左)をすぎ
(山門=昔、勅使が興津川の氾濫で東光寺に泊まる事になり急遽この門を造った)
庵原川橋あたりで緑みかん(無人販売1袋100円)を買う。
少し硬いけど中味は甘かった。もしかして薩垂峠のみかんは食べられた
のかも知れない。
国道右側に「馬頭観世音菩薩」(写真中)を見ながら、やがて道路は二又に分かれるが
そこに「細井の松原」(現在は写真右の一本だけ)があった。右の旧道を行き15時:清水駅に到着。
東光寺山門(写真左)をすぎ
(山門=昔、勅使が興津川の氾濫で東光寺に泊まる事になり急遽この門を造った)
庵原川橋あたりで緑みかん(無人販売1袋100円)を買う。
少し硬いけど中味は甘かった。もしかして薩垂峠のみかんは食べられた
のかも知れない。
国道右側に「馬頭観世音菩薩」(写真中)を見ながら、やがて道路は二又に分かれるが
そこに「細井の松原」(現在は写真右の一本だけ)があった。右の旧道を行き15時:清水駅に到着。
・・・午後16時:旅人は「ビジネスホテルときわ」のコインランドリー前でコーヒーを飲んでいた。 (行程2時間(計5時間) ・1999.9/23(木):万歩計=29841) |
旅人:浮浪雲
18.由比宿〜興津宿へ
 20.江尻宿〜府中宿へ
20.江尻宿〜府中宿へ
|